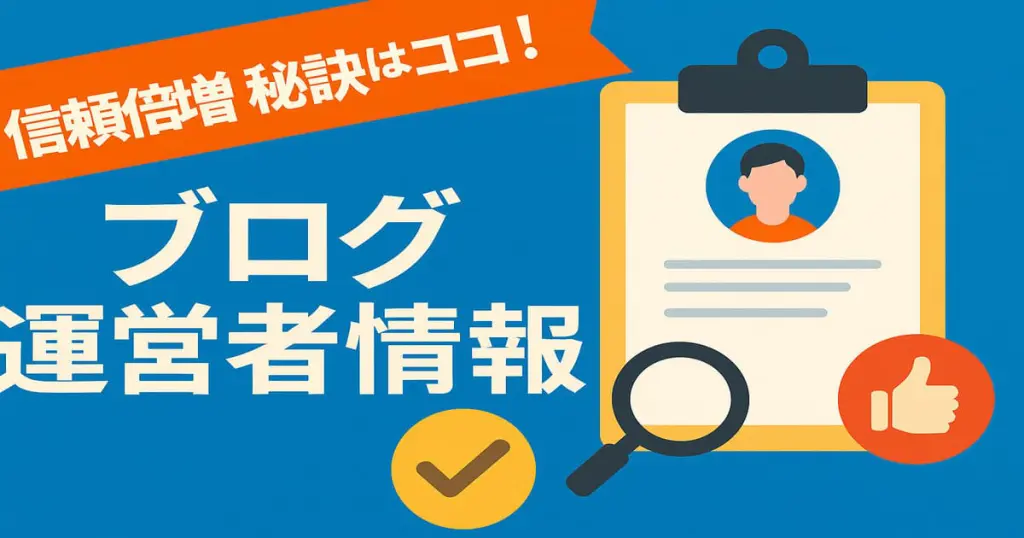
こんにちは。正しいサイト構築&SEOアドバイザーの田村です。
あなたは次のことで悩んでいませんか?
- ブログの運営者情報をどのように書いたら良いのかわからない
- ブログの運営者情報はどう作ったら良いの?
- ブログの運営者情報とSEOとの関係は?
そこで本記事では、ブログの運営者情報の書き方について10個のポイントをご紹介します。
10個のポイントについて書くと、信頼性を得やすくなり、商品が売れる可能性を高める運営者情報を書くことができます。
また、運営者情報の作り方やSEOとの関係性まで解説していますので、最後までご覧いただければと思います。
さらに、この記事の内容を動画でもわかりやすく解説しています。文章より動画で理解したい方は、こちらもぜひチェックしてみてください。
なぜブログに運営者情報が必要なのか?

ブログを訪れた読者は、「誰が書いているのか?」を自然と気にしています。
また、Googleもコンテンツの品質評価において、発信者の情報を重視するようになっているわけですね。
とはいえ、単に名前や肩書きを載せるだけでは不十分な場合もあります。
では、具体的にどんな影響があるのか?
以下の3つのポイントをぜひご覧ください。
- 信頼性やSEOに与える影響
- 「EEAT」との関係性
- ユーザーの不安や疑問を払拭する効果
信頼性やSEOに与える影響
運営者情報を明確に示すことは、ブログの信頼性を高める強力な要素です。
たとえば、同じ内容の記事でも「誰が書いているか」が明確な方が、ユーザーは安心して情報を受け取ることができます。特に体験談やレビュー系のコンテンツでは、発信者の立場や経験が見えるかどうかで、受け取り方が大きく変わります。
そして、この“信頼性”は、検索エンジンにも評価されるポイントです。Googleは近年、「信頼できる情報源からの発信であるか?」を重視するようになっており、運営者の専門性や実績が明記されているページは、E-E-A-Tの観点からもプラス評価を受けやすくなっています。
特に、健康・お金・育児・法律など、人生に関わるジャンル(YMYL)では、誰が書いているのかが分からないサイトは上位表示されにくい傾向があります。
つまり、読者にとってもGoogleにとっても、運営者情報は「このブログは信頼していいのか?」を判断する重要な材料なのです。
「EEAT」との関係性
Googleの品質評価ガイドラインでは、信頼できる情報かどうかを評価する際に「EEAT」という基準が使われています。これは、以下の4つの要素の頭文字を取ったものです。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trust(信頼)
この中でも「Trust(信頼)」は最も重視されており、運営者情報はそれを支える重要な要素とされています。
たとえば、実体験をもとにした発信(経験)や、専門的な知識に基づく内容(専門性)を語る際に、「誰がそれを語っているのか?」が分からなければ、説得力も信頼性も落ちてしまいます。
運営者の経歴や資格、実績を記載することで、その人がそのテーマについて語る根拠が伝わり、「EEAT」のすべての要素を強化することができます。
特に、YMYL領域では、運営者情報が不十分なだけで信頼性の低いページと判断され、評価が下がる可能性もあります。
だからこそ、単なる自己紹介にとどまらず、「なぜこのテーマを扱っているのか?」「どんな知識や経験があるのか?」を伝えることが、SEO的にも重要なのです。
ユーザーの不安や疑問を払拭する効果
ユーザーは、ネット上の情報に対して常に「この情報は本当に信じていいのか?」という不安を抱えています。特に個人ブログやアフィリエイトサイトでは、広告目的の記事やステマを警戒している人も少なくありません。
そんなとき、運営者情報がしっかり記載されていると、「このブログは誰が運営しているのか」「どんな思いで書いているのか」が伝わり、読者の警戒心を和らげることができます。
たとえば、実体験に基づく発信や、プロフィールに書かれた経歴・実績などは、「この人の言うことなら信じられる」という安心感につながるわけですね。
また、問い合わせ先やSNSリンクがあれば、「何かあったときに連絡できる」という透明性が信頼を後押しします。
つまり、運営者情報は「不安を解消する」だけでなく、「信頼につなげ、記事を最後まで読んでもらう」効果もあるのです。
ブログの運営者情報の書き方10個のポイント
ブログの運営者情報の書き方のポイントを10個ご紹介します。
- 実名、またはニックネーム
- 顔写真、またはアバター画像
- 出身地や年齢
- 情報発信しているジャンル
- そのジャンルを選んだ理由
- 経歴
- 実績
- ユーザーへの想い
- SNSなどのリンク
- 問い合わせフォーム
それでは、一つずつ詳しく解説します。
実名、またはニックネーム
収益化を目的にブログに取り組んでいるならば、実名が理想です。
なぜなら、信頼性が増すので収益につながりやすくなるからです。
ですが、副業などで実名を避けたい方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、ニックネームでもかまいません。
顔写真、またはアバター画像
ブログの成功確率を高めるなら、顔写真が良いです。
理由は信頼性が高まり、収益につながりやすくなるからです。
しかし、副業の関係で顔写真が厳しいなら、アバター画像でも問題ありません。
基本情報
基本情報として、出身地や年齢、趣味などを書くと良いです。
長々と書くのではなく、簡潔に書きましょう。
ユーザーがあなたと少しでも接点があれば、親近感がわきやすくなります。
親近感がわけば、信頼性が少しでも高まりやすくなり、収益につながる可能性を高めることができます。
情報発信しているジャンル
ブログでどんなジャンルについての情報を発信しているかを書くと良いです。
「専門家」や「○○に詳しい人」をアピールできます。
今の時代は、情報が山のように溢れているので、信頼できるブログ、つまり専門的なブログのほうがユーザーに読まれ、収益につながりやすいです。
そのジャンルを選んだ理由
情報発信しているジャンルについて記載したら、そのジャンルを選んだ理由を書いたほうが良いです。
例えば、ダイエットに関するブログを運営しているとします。
なぜ、ブログでダイエットに関する情報を発信しようと思ったのかを考えるということです。
もちろん、収益のためだとは思いますが、それをそのままユーザーに伝えては信頼性を損ないます。
ですから、「自分のダイエット経験を活かして、ダイエットに悩む人のお役に立ちたい」のようなことを書いた方が良いです。
すると、ユーザーに好感を持たれるようになり、収益につながる可能性を高めることができます。
経歴
ここで言う経歴とは、学生時代のアルバイトや現在のお仕事のことではありません。
選んだジャンルに関係した経歴です。
例えば、ダイエットに関するブログを運営しているとします。
過去に半年間、ダイエットをしたことがある場合、それ経歴と言えます。
もし、ダイエットをしたことがなく、ダイエットに関する経歴がない場合、作れば良いのです。
例えば、実際にダイエットをしてみることが挙げられます。
また、ダイエットに関するブログを半年間、運営している場合、「半年間、ブログでダイエットに関する情報を発信している」ことも経歴とすることができるわけです。
つまり、経歴がなければ作りましょう。
もちろん、ウソはダメです。
実績
ここで言う実績もまた、ジャンルに関係した実績を書いたほうが良いです。
そうすることで、そのジャンルの専門性をアピールすることができ、信頼性を高めることができます。
例えば、ダイエットに関するブログを運営している場合、「ダイエットで5キロ痩せた」などが実績として挙げられます。
もし、実績がなければ、実績を作る努力をするのです。
実績を伝えることで、その分野の専門性を伝えることができ、信頼へとつながり、商品が売れる可能性を高めることができます。
もちろん、ウソの実績を書いてはいけません。
ユーザーへの想い
ユーザーにブログを読んでもらい、ユーザーにどうなって欲しいのかを書くと良いです。
いわゆる理念のようなものです。
例えば、ダイエットに関するブログを運営している場合、「ユーザーがダイエットに成功し、自分に自信をもってもらいたい」などが挙げられます。
ユーザーに共感をもたれるようになれば、リピーターやファン化につながり、ブログを読み続けていただけたり、商品を購入し続けたりする可能性があるわけですね。
SNSなどのリンク
運営者情報の最後に、SNSなどのリンクを貼っておくと良いです。
ブログ経由でSNSにも誘導することで、あなたのことをより深く知ってもらえます。
信頼性の獲得につながるわけです。
SNSはXやInstagramなどが挙げられます。
問い合わせフォーム
ユーザーからの質問やフィードバックを受け取れる問い合わせフォームは、信頼性を高める要素のひとつです。運営者との連絡手段が明示されていることで、「何かあったときに連絡できる安心感」が生まれます。
特に商品紹介やアフィリエイトを行っている場合は、透明性の確保という意味でも設置しておくのがおすすめです。
なお、すでに「お問い合わせページ」を別で設置している場合は、運営者情報ページ内に詳細を記載しなくても構いません。その場合は、「お問い合わせはこちら」などとリンクで案内するだけでも十分です。
ブログの運営者情報を作る方法

ブログの運営者情報は、WordPressでブログを作っている場合、固定ページで作ることをおすすめします。
なぜなら、何千、何万文字と多くの内容を書くことができるからです。
伝える内容が多いほど、あなたについて多くのことをユーザーに知ってもらうことができます。
つまり、商品が売れる可能性を高めることができるわけです。
固定ページの他に、サイドバーや各記事の下部に書くという方法があります。
サイドバーに運営者情報を掲載した場合、スマホでブログを見る際に、サイドバーに設置した内容は一番下に表示されます。
スクロールされないと、見られないわけですね。
また、各記事の下部に運営者情報を記載した場合も、下にスクロールしないと見られません。
一方で、固定ページで作成した運営者情報をグローバルナビゲーションに設置すると、スマホで見た際に上部にメニューが表示されるので、スクロールせずにそのメニューから運営者情報をチェックすることができるわけです。
ご利用のテーマによって、メニューの表示箇所が異なるかもしれません。
ですが、いずれにせよ、スクロールしなくてもメニューを開ける形になっていると思います。
ですので、運営者情報は固定ページで作成し、グローバルナビゲーションに設置することをおすすめします。
匿名や副業バレを防ぎたい場合は?

ブログを副業として運営している方や、プライバシーを守りたい方の中には、顔出しや実名公開に抵抗がある方も多いはずです。
しかし、匿名でも信頼される運営者情報の書き方は可能ですし、SEOや読者への配慮も十分に両立できます。
具体的な方法は、以下の3つの見出しで詳しくご紹介しています。
- 顔出し・実名NGのときの工夫
- 匿名でも信頼される書き方
- 最低限必要な情報とは
「見せない」ことに悩むより、「何をどう見せるか」を工夫していきましょう。
顔出し・実名NGのときの工夫
副業でブログを運営している方や、プライバシーの観点から顔出し・実名を避けたいという人は多いはずです。ですが、匿名だからといって信頼されないわけではありません。
重要なのは「読者が不安にならない情報開示の仕方」を工夫することです。
たとえば、以下のような方法があります。
- ニックネームを一貫して使う(SNSと統一するとなお良い)
- アイコン画像を自分らしいイラストや雰囲気のある写真にする
- 発信ジャンルとの関係性や、発信の背景を丁寧に説明する
- 連絡手段やSNSアカウントを明記し、透明性を確保する
こうした工夫により、たとえ匿名であっても「この人の情報は信頼できそう」と感じてもらいやすくなります。
匿名でも信頼される書き方
たとえ本名や顔写真を出さなくても、ユーザーから信頼されるプロフィールは作れます。大切なのは「なぜこの情報を発信しているのか」と「どんな経験に基づいているのか」を伝えることです。
たとえば、以下のような要素を含めることで、匿名でも信頼性を高められます。
- 発信ジャンルを選んだ理由や背景(体験談など)を具体的に書く
- 過去の経験・失敗談・成功例を交えて、実体験があることを示す
- 専門性が伝わる実績やスキル(資格・職歴・活動歴)を明記する
- ペルソナに寄り添った言葉選びで、ユーザーとの距離を縮める
匿名でも「この人の言葉はリアルだ」と思ってもらえれば、名前の有無は大きな問題にはなりません。
最低限必要な情報とは
匿名でブログを運営する場合でも、「まったく何も書かない」というのはNGです。ユーザーや検索エンジンに不信感を与えないためには、最低限の自己開示が必要です。
以下の情報は、匿名でも載せておくべき基本項目です。
- ニックネーム(一貫して使える名前がおすすめ)
- どんなテーマを発信しているか
- そのテーマを選んだ理由や背景(体験談や問題意識)
- 発信者としての立場(例:元○○、経験者、利用者目線など)
- 問い合わせ先やSNSなど、ユーザーが連絡できる手段
これらを明確にしておくだけでも、「このブログは誰かが責任を持って書いている」と伝わり、信頼感がグッと上がります。
ブログの運営者情報とSEOの関係性

SEOに取り組んでいると、運営者情報とSEOの関係性が気になるかと思います。
結論を言うと、関係している可能性は高いと言えます。
なぜなら、Googleの公式ページで高く評価されるためには、「誰が、どのように、なぜ」を考えることが大切と公表しているからです。
また、Googleは「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」という概念を大切にしていますが、この概念を高めるには運営者情報が必須と言えるでしょう。
ですので、運営者情報とSEOは関係があると考えています。
現在は溢れるほどの情報が存在します。
そのため、何が正しくて何が間違いなのかを判断することが難しいわけです。
そこで、「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の高いサイトを、検索エンジンは高く評価している可能性があるわけです。
検索結果の上位を見ると、「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の高いサイトである傾向にあります。
したがって、「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を高めるために、運営者情報をしっかり書くことを強く推奨します。
まとめ
本記事では次のことについて解説しました。
- なぜブログに運営者情報が必要なのか?
- ブログの運営者情報の書き方10個のポイント
- ブログの運営者情報を作る方法
- 匿名や副業バレを防ぎたい場合は?
- ブログの運営者情報とSEOの関係性
ブログの運営者情報はしっかりと書いたほうが良いです。
なぜなら、SEOに関わっている可能性が高いからです。
ですから、お伝えした10個のポイントを意識して、ブログの運営者情報を執筆していただければと思います。
なお、SEOに強いブログを作るための実践ノウハウは、無料メルマガ講座でも詳しく解説しています。
これから本格的にブログを伸ばしたい方は、ぜひこちらからご登録ください。
※本記事は、SEOアドバイザーである私、田村がしっかりと確認した上で生成AIツールを活用しております。
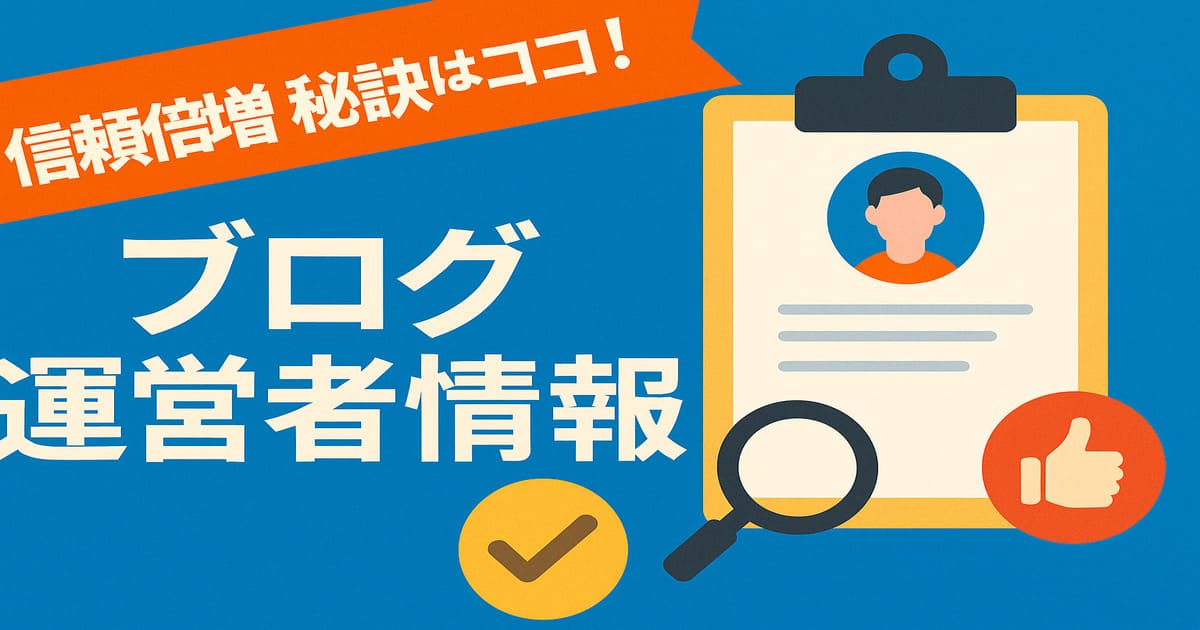
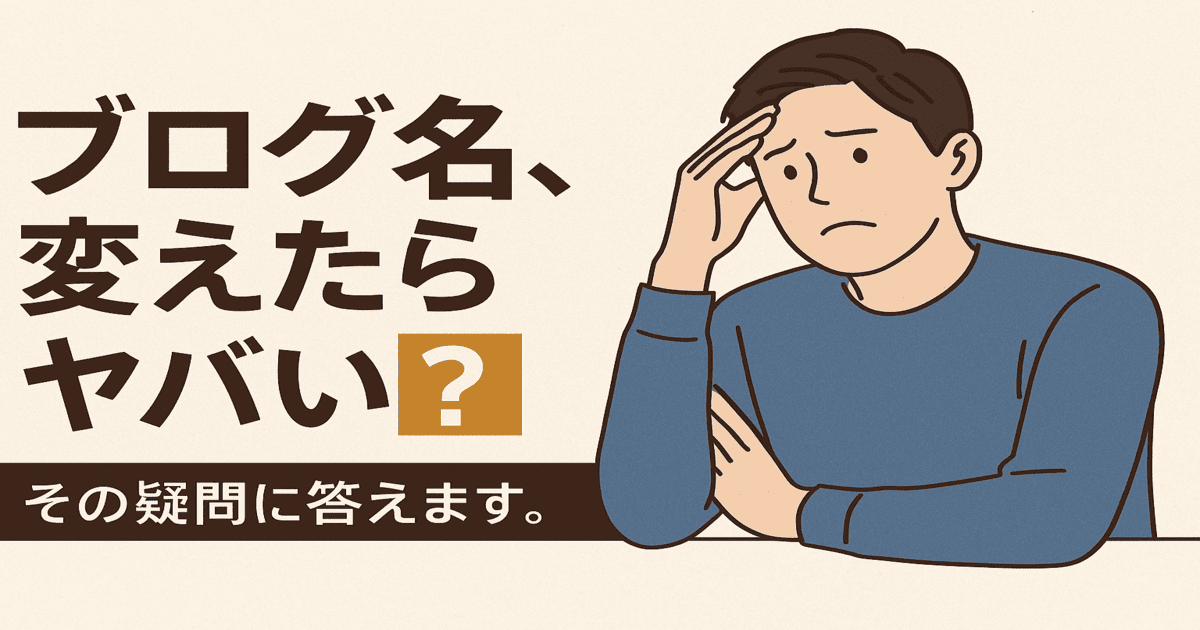
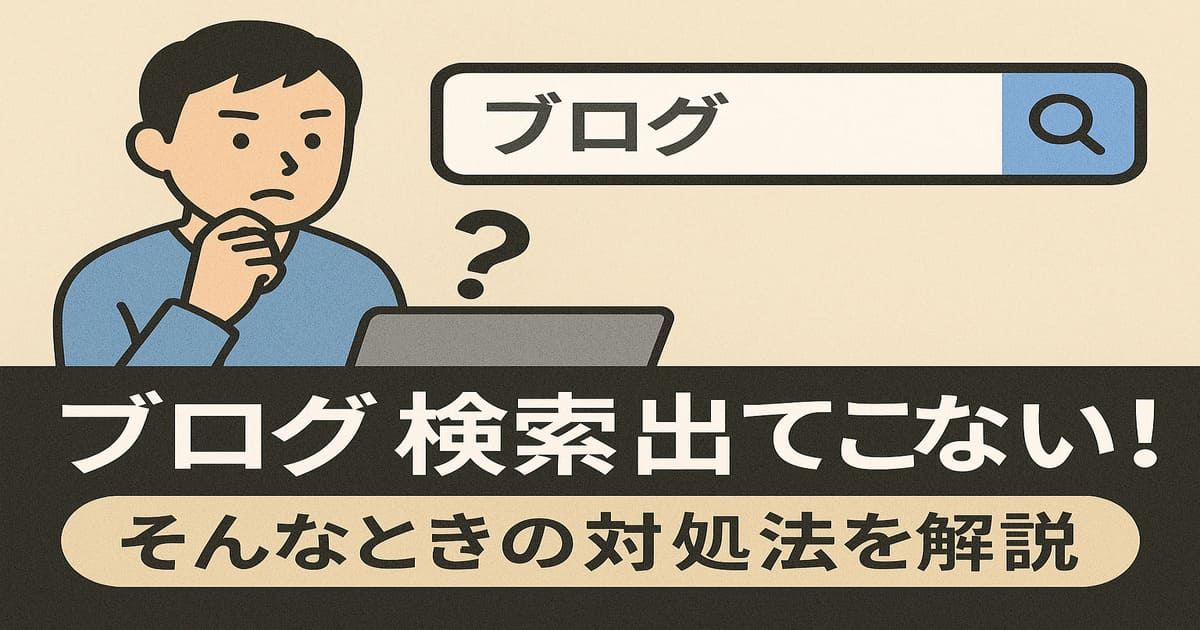
コメント